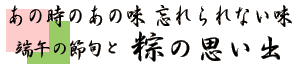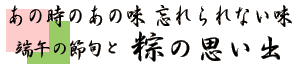薫風かおる、爽やかな季節になってきました。5月5日は端午の節句です。端午の端は、はじめという意味で、端午は月のはじめの午の日ということになります
もともと中国から伝わった行事ですが、端午の日は野外にでて、「百草の戯」といって、薬草を摘んだり、また高い薬効をもつ、菖蒲をひたした酒を飲んだりして、邪気を祓い、無病息災を祈る風習から始まったと記されていました。
日本に伝わってからは、時代を経て、「菖蒲」が、「尚武」に通じるところからそれまでの、単なる厄よけの行事でなく、男子の成長と武運を祈願する祭礼と変わったと言われています。また、節句のお飾りとして、鎧や兜、五月人形を飾りますが、お供えとして、柏餅と粽を供えます。
よく調べてみると、5月の粽も、中国の賢人、屈原というひとの死を悼む供養の伝説からきているようです。毎年、5月5日に竹筒に米をいれ、水に投じて祈っていたのが、後に、木の葉で米を包み、糸でしばった粽になったようです。日本に伝わってからは、笹の葉でつつんだ、おしんこ餅や、葛のお菓子として、作られるようになりました。
|
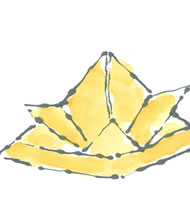 |