
筍とわかめのであいもん若竹煮 |
程よくお腹のすいた頃に、美山荘に着きました。美山荘は代々、峰定寺の宿坊だったのですが、三代目さんが摘草料理を始められ、料理の素材や、凝った器等、いつも心のこもったお料理ですが、あの時の「筍といたどり」の煮物の味は今もはっきり憶えています。我が家ではとても、あれほど分厚く筍を切れませんが、なぜか素材をいかしながら、あの分厚く切られた筍に味がしみているのです。そして筍のであいもんは、いつもなら「わかめ」なのですが、
この時はいたどりでした。いたどりは、桜の花の終わるころ、おまたせしましたとばかりに、20センチ位のアスパラのようなものから、一メートル程になるそうです。ただとても酸味がきついので、湯をかけて一昼夜つけるそうです。
おおば先生が、京都の桜の終わる頃に来ていただいたお蔭で、常照皇寺の「九重の桜」も楽しめましたし、いままで知らなかった「いたどり」も賞味することが出来ました。
これも、先生との出会いがあり、いろんなものや、おいしいものの出会いが、いかに大切な事か、改めて思いました。おたべを売り出して40年、初心に戻る事が大事だと思いますが、ホームページも5年目に入りました。もう一度見直して、やっていきたいと思います。
|
| 「美山荘」 |
京都市中心地から約40km。洛北の山里・花脊の大悲山峰定寺の門前にある、料理旅館。
山野草を主に、川魚など山と川の天然素材を調理した摘菜料理が有名。 |
|
| 「いたどり」 |
春の野菜。シュウ酸が含まれていて酸味があるので、皮をむき熱湯の中に入れて冷めるまで待ち、酸味が殆ど無くなったところで料理をする。水にさらして煮たり炒めたりして食べる。夏には背丈ほどにもに生長し夏の終わりに白い花が咲く。 |
|
| 「であいもん」 |
出会いもの。出会いによってお互いの味を引き立て、栄養のバランスも彩りも良い、昔からの美味しい組み合わせ。
筍とわかめ、身欠きニシンとなす、いかと小芋、棒たらと海老芋、揚げ豆腐と水菜、ぶりと大根・・・など。 |
| ←3月は「ひな祭り」 |
|

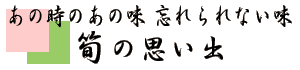 5月は「粽の思い出」→
5月は「粽の思い出」→ 
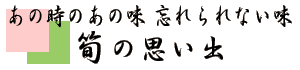 5月は「粽の思い出」→
5月は「粽の思い出」→