
↑赤じそ |
1: 本漬けしょうと思う頃、赤じそが売っているのです。 |

↑葉だけをとる |
2:葉っぱだけを取り、何度も塩もみします。山のような赤じそは、ほんの少しになってしまいます。 |
| |
|
↓塩もみする |
|
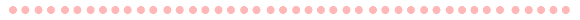 |

↑赤くなりました |
3:塩もみした赤じそに白梅酢を入れると、本当にきれいな赤紫になります。 |

↑漬け込みます |
4:塩漬けした梅と、赤紫のしそと交互に漬け、土用干しの日まで待ちます。 |
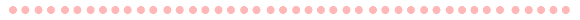 |

↑並べて干します |
5:土用(7月20日ごろ)のお天気のいい日に、梅干としそうをざるに並べ、日光と夜露にあててください。祇園祭りも終わって真っ赤にきれいに色づいた梅を干す時が、至福の時です。
|
|
|
<福井梅について>
福井県の梅には梅干し用の「紅映梅・べにさしうめ」と、梅酒用の「剣先・けんさき」という梅の2種類が有名です。梅干し用の「紅映梅・べにさしうめ」は紅映というその名のとおり、梅の表皮が熟するに従って鮮やかな紅色に染まり、芳香を放ちます。種が小さく、果肉が厚いという特徴があり、やわらかく繊維のすくないおいしい梅干ができあがります。一度、試してみてはいかがでしょう?
|











