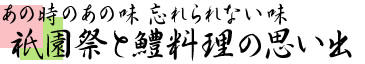|
京都の夏といえば祇園祭一色になります。山鉾の一つ、北観音山の山鉾町で生まれ育ち、南観音山の百足屋町に嫁いで来た私は、長年祇園祭に携わって来ました。
おたべが借りている南観音山の町会所の一階が、新町店になっています。町会所とは、祇園祭りの神事や町内の会合、祇園囃子のお稽古等に使う町有の建物です。町会所の奥には、山鉾を収納している蔵もあります。お祭り以外の時期は二階を、おたべの体験道場としても使っています。
|
6月に入ると、何千という粽が町会所の二階に届きます。今年は、六月二十三日に町内の人たちが集まり、粽の一つ一つに「蘇民将来之子孫也」と書かれた赤いお守り札を取り付けました。この食べられない粽は、翌年の祇園祭まで一年間、疫病や災難除けとして門口につるしておきます。八坂神社の神様の、スサノオノミコトを手厚くもてなした蘇民将来の子孫は、粽をつけておけば災危から免れるという故事からきているのです。
いよいよ7月1日の吉符入りの日には、八坂神社から神主さんに来てもらい、祭りの無事をご祈祷して頂きます。この日から町会所の二階で祇園囃子の稽古が始まります。そして、12日のお山立て、13日の曳き初めと行事が進み、16日の宵山、17日の祭りのハイライトである山鉾巡行の日を迎えるのです。
|
扇子とてぬぐい
|
|
南観音山
|
この山鉾巡行は、今は32基の山と鉾が、毎年長刀鉾を先頭に巡行しています。昭和40年までは、17日の先祭りと、24日の後祭りに分かれていました。長刀鉾は先祭りですが、北観音山と、南観音山は後祭りでした。後祭りの巡行のコースは、北観音山を先頭に、新町三条、三条寺町、寺町四条、四条新町、新町蛸薬師に戻ってきました。最後はいつも南観音山と決まっていましたが、今もそれは変わっていません。
先祭りと後祭りが一緒に、17日に祇園祭りがされるようになったその年の7月14日に、おたべちゃんのおにいさんが、誕生しました。そして、その8月1日から「おたべ」を発売したのでした。
お祭りに生まれたせいではないのですが、おたべちゃんのおにいさんが、小学生の五年の時に、長刀鉾の稚児を勤めました。長刀鉾の子供になるという、納采の儀から始まり、吉符入りや、八坂神社に正五位の位をもらいにいく、社参の儀等がありました。色々の行事の度に、白塗りのお化粧をして、立派な衣装をきせてもらい、おにいちゃんが、だんだん、お稚児さんらしくなっていく様子を、幼いおたべちゃんは一生懸命くいいるように見ていました。おたべちゃんのおにいさんは、本当に位をもらったわけではないのですが、17日の巡行を無事に立派に勤められました。
|
祇園祭りにとってもう一つ欠かせないものに、鱧料理があります。北観音山にあった京料理の仕出し屋をしていた私の実家は、お祭りはそれはそれは忙しくしていました。少し頑固だった父でしたが、大きなまな板の置かれた板場で、透きとおるような白い身の鱧を、大きな骨切り包丁で、シャリシャリと音をたてながら、骨切りしているのを見るのが大好きでした。山椒の実の入っている父の作る鱧寿司は、これまた絶品でした。
今は、二条室町にある堺萬の鱧寿司が、美味しいです。鱧の焼きがべとづかず、さりとてぱさづかず、寿司めしとの調和が、絶妙だと思います。
お祭りが近づいてくると、「今年は堺萬(※1)さんに、鱧寿司を何本注文したらええのかなー」といつも思案します。そしてお客様には、この鱧寿司の他に、鱧おとしや、鱧の南蛮漬け等、私の手づくりの鱧料理を出しています。
父が他界した後、仕出し業は廃業しましたが、祇園祭りがくる度に父の味を思いだします。やっぱりお祭りは、私のお料理の原点になっているような気がします。
「堺萬」(※1)
創業文久3年(1863年)。京都ならではの鱧をはじめ、旬の素材を使う伝統的な京料理の名店です。
|