| 《今月のおばんざい》です。「おばんざい」とは、京都のお母さんの味、お惣菜のことです。旬の食材をつかった 簡単なおばんざいをおたべちゃんのお母さんにお聞きします。 |
| おばんざいの基本、だしの取り方はこちらを参考に! |

| すこし早いと思いますが、赤い京人参が出てきました。甘くて色鮮やかで、粕汁や、かやくご飯、筑前煮にいつも使います。筑前煮とは、九州博多地方が水だきをはじめ、鳥料理が有名な事からついた名前のようです。その季節の野菜を上手に使って、お正月や、また年中重宝する一品です。白和えも、その時の季節の野菜でしてください。大根や胡瓜には、甘辛く炊いた椎茸があいますね。そして、11月紅葉の時の紅葉麩は、お料理を目でも楽しませてくれます。麩はさっと湯がく事でとてもあつかいやすくなりますよ。 | |||
 |
 |
|
 |
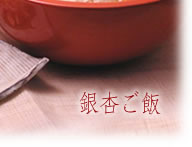 |
| 金時人参、京人参と親しまれている、赤色の鮮やかな京野菜です。西洋人参とは赤の色合いがかなり違うので、一目でわかるでしょう。表面だけでなく、芯まで真っ赤で、肉質はやわらかく、煮くずれしにくく、甘みがあります。京都ではお正月のおせちには必ず、金時人参を使い、粕汁や煮物など冬の料理の彩りとして欠かせません。 |











